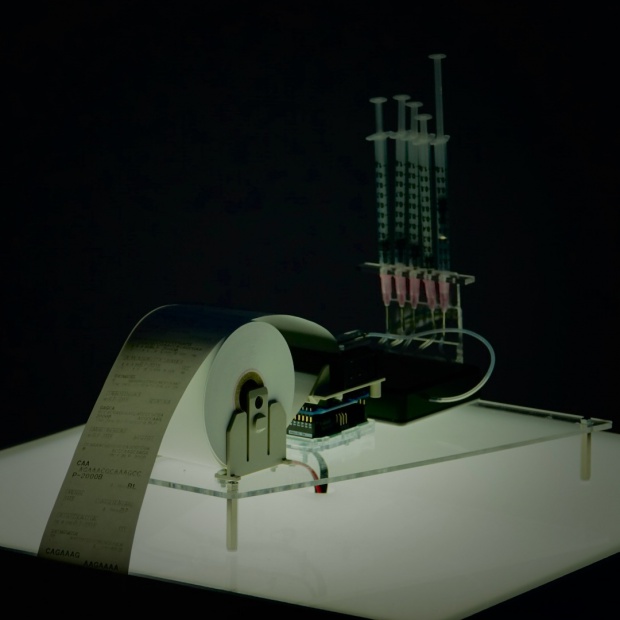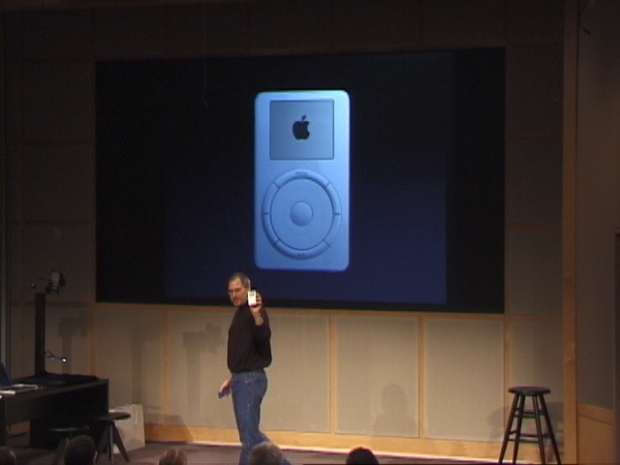COVID-19からのBuild Back Better
戻るべきはどの世界?
“Build Back Better”という言葉がある。
私は東日本大震災の直後に知った。
大きな自然災害で破壊された街の復興。
元の通りに戻さねばと考える人が多い。
でも、そうではなく「前よりも良い状態にする」のがBuild Back Betterだ。
災害への備えの点でbetterという意味で使われることが多い。
ただ、もう少し拡張して、そもそも問題を抱えていた街を、
カタストロフィーを1つのリセットボタンと考えて、もっと良い状態で再創造するという意味にも使えないだろうか。東日本大震災の多くの被災地も、震災前、既に経済の落ち込みや過疎化といった問題を抱え、先行きのない状態に陥っており、膨大な時間と労力をかけて未来のないままの街に戻すことは無意味だと多くの人が議論していた。
同じことは、今年に入ってから人類を襲った新型コロナウィルス感染症(COVID-19)のパンデミックに対しても言うことができる。
COVID-19が牙をむく前、世界では気候変動による大規模災害が大きな関心事で、世界の若者たちが対策の必要性を訴え立ち上がっていた。
各国の代表者たちも、重要性は認めたものの「すぐには実行できない」と気の長い目標を示していた。
だが、パンデミックで、世界中の大都市が、経済活動の自粛をしたことで、今、地球上の大気はここしばらくなかった水準で浄化されている。3月時点で、二酸化炭素の排出量が中国だけで2億トン(約25%)減少、4月時点でPM2.5の量がインドのニューデリーで60%、韓国のソウルで54%減になったという。ヴェネツィアの水もかつてない透明度を取り戻したと話題になっている。
ここで我々に突き付けられるのが次の問いだ:
「もし、ワクチンなどが開発され、COVID-19の流行が抑えられたら、我々は膨大なCO2を排出し、大気を汚しまくっていた経済活動に本当に戻って良いのか」
まだ査読中のものが多いが、大気汚染とCOVID-19の関連性を調査した論文が増えている。イタリアのボローニャ大学では、大気汚染の原因粒子にのってCOVID-19が拡散していた可能性を指摘している。一方、米ハーバード公衆衛生大学院(HSPH)の研究チームも大気汚染と感染致死率の関連性を指摘している。
そもそも昨今の感染症の多くは人間が自然を破壊し、不幸な動物たちの交わりが起きたことが原因というのが、COVID-19禍で大きな注目を集めた感染症映画「コンテイジョン」のラストシーンの示唆であり、アップル社のThink Differentキャンペーンにも登場した霊長類学者ジェーン・グドールの主張だ。
この数ヶ月の経済的ダメージを考えると、今は緊急事態で「もはや環境のことなど考えている余裕もない」という人も少なくないだろう。しかし、そうやって元の活動に戻ってしまったら、そこから一体どうやって将来の「環境改善」に取り組むというのだろう。
こうしたことを踏まえ、我々はどのように経済活動を再開していくのか。
日本はイタリアに比べたら空気がきれいだし、我々には関係ない?では、日本人でなく、イタリア人にはなんと勧める?あなたたちは、これまで通りの経済活動に戻って空気を汚してください?
経済活動再開、その進路は?
COVID-19のパンデミックがもたらしたのは環境の変化だけではない。
日本の社会にも、もはや不可逆となりそうな変化をいくつももたらしている。
改めてパンデミック前後の世の中の変化を振り返ってみよう。
日本では常に東京一極集中が問題とされてきたが、変化をまっさきに求められたのは東京などの大都市で、この後も地方都市から先に緊急事態宣言が緩和され、東京などの大都市だけつづく可能性が高い。
そんな東京。オリンピックでの交通混雑を解消するのに必要だと言われていたにも関わらず、なかなか広がらなかったテレワーク(リモートワーク)。これがCOVID-19による外出自粛で、一気に普及した。
テレワークで、大きな障壁となっていた印鑑の利用もIT担当相の失言が最後のひと押しとなり一気に進むことになった。
こうやって家で働くことが増えれば、自然と裁量労働制へのシフトが進む。
過労による自殺などが話題となり「働きかた改革」の重要性が訴えられていたが、政府が主導していた働き手のモチベーションを無視した就業時間だけで規定する雑な「働きかた改革」よりもよほど本質的な働きかた改革になる。
同時に女性にとって働きやすい仕事環境の整備にも追い風になるはずだ。
就労に関する問題といえば、都知事が公約しつつも、なかなか解決できずにいた東京の満員電車の問題も、COVID-19流行によるオフピーク通勤やテレワークで、いとも簡単に解消されてしまった。お勤めの方々は、これだけ長く平穏を味わった後で、本当にあの人を人とも思わぬ劣悪環境に戻ることができるのだろうか。
皆、どこかで答えはわかっているはずだ。
しかし、ネットで実際に経済活動を再開しようとしている人たちの声やアクションに目を向けてみると、必ずしもその方向性は合致していない。
我々の頭の中にある「仕事のイメージ」は、多くの問題をはらんだままの昨年までの仕事のやり方のイメージだ。
そもそも会社の組織構造であったり、収益源/ビジネスモデルであったり、想定している顧客であったり、収益目標であったりも、昨年のままである。
これまでずっと「一度、立ち止まって本当にこのままでいいのか話し合う必要がある」。
おそらくすべての業界に、そういう声をあげる人はいた。
今、人類は、まさにその立ち止まり、話し合うべき機会を半ば強制的に与えられている。
しかし、中国はそれをしないまま、経済活動の再開への一歩を踏み出し、その立場を利用して世界中で先行者利益の獲得をしようと営業活動を活性化している。
アメリカやヨーロッパも、それに続こうとしている。
と、なれば資本主義の競争からこぼれ落ちないためにも、早実、日本も同じ道をたどり始めるだろう。
そして人類は、再び昨年までの世界に戻っていく。次の大規模災害までの束の間…
おそらく数年間に3度くらい連続でこの規模の災害に見舞われないと、人類はその姿勢を正さないのではないかというあきらめをどこかで感じる。
しかし、それはなぜだろう?と問いただすと、より根源的な問題が見えてくる。