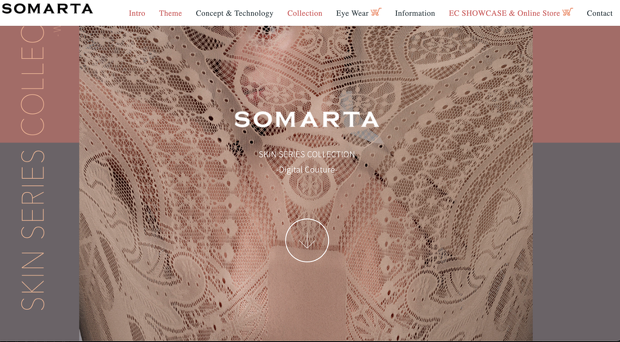拡張を続ける廣川玉枝の「皮膚のデザイン」
下記の文は、元々は2024年10月から12月まで藤沢市アートスペースにて開催されていた廣川玉枝展「皮膚のデザイン」の図録に寄稿したものだ。
長年、廣川さんの活躍を近くで見てきた経験を活かして我ながら渾身の記事を書いたつもりだったが、廣川さんも気に入ってくれて、ぜひもっと多くの人に読んでもらいたいということになり、藤沢市アートスペースの許可も得て、こちらに転載する運びとなった(同時に英語版も作成してこちらで公開している)。
The English version of this article can be found [here].
皮膚のデザイン:固定観念を超えた創造性の探求
船が難破したとしよう。救命ボートもすべてなくなった。
見ると、ピアノの上板が流れてくる。これが捕まっても十分浮力があるものなら、思いもかけない救命具になる。といって、救命具の最良のデザインがピアノの上板だというわけじゃない。偶然手に入れた昨日の思いつきを、与えられた問題に対する唯一の解決策だと信じ込んでいるという点で、私たちはじつに多くのピアノの上板にしがみついているのだと私は思う。
バックミンスター・フラー著、芹沢高志訳
『宇宙船地球号 操縦マニュアル』より
我々が日常生活で「それが当たり前」と受け入れているものの多くは歴史の偶然の産物で、本来もっと色々あっていいはずの可能性の一つに過ぎない。毎朝起きた後、当たり前に着替える洋服も「西洋」の服という無限にある衣服の可能性の一つに過ぎず、唯一の答えではない。明治以前の日本人は、今でいう「和服」を当たり前に纏っていた。洋服とは作り方、纏い方、そして根本の概念もまったく異なる「服」だ。
日本人が和服から洋服に乗り換えたからといって和服が劣っているわけではない。実際、19 世紀後半に西欧で広まった日本趣味(ジャポニスム)の流れの中で「着物」が大きな注目を集め、多くの西洋画に描かれた他、ポール・ポワレ含む多くの服飾デザイナーに影響を与えた。
とはいえ、21 世紀現在、世界の「服」の主流は洋服だ。そしてファッションの世界のデザイナーのほとんどはこの「洋服」というフォーマットの上で、他と差別化する装飾的工夫を施している。これは日本も同じで、今日、服飾デザイナーと言えば、そのほとんどが西洋服のデザイナーとなっている。
一方で、そもそもの「服」のあり方を根本から見直そうとするデザイナーが少なくないのも日本の特徴だ。かつて廣川玉枝が所属していたイッセイ ミヤケの創業者、三宅一生はその代表格だろう。そんな三宅に学生時代から才能を認められ、大きな影響を受けてきた廣川玉枝も、服造りの概念を根本から見直すデザイナーの注目株となっている。
三宅一生は、日本の着物にも通じる「一枚の布」という視座を獲得し、そこに軸足を置きながら新しい服のあり方を模索した。この視座は氏が逝去した今日でも、誰も見たことのない新しい服やその他のアイテムを生み出し続ける源泉となっている。
同様に廣川玉枝も、新しい視座を獲得し、それが活動の軸足になっている。その視座こそが、展覧会のタイトルにもなっている「皮膚のデザイン」だ。確かに服の可能性は無限にある。しかし、衣服は人の肉体を包む人工的に作られた「外皮」であり、「第二の皮膚」である、というのは揺るぐことがない本質であり、地域や民族、文化が異なっても変わらない共通項だ。彼女はここに目をつけた。
この視座を得て、廣川は自らの役割を「皮膚のデザイナー」と定義した。この視座で、彼女は各国の環境や風土に基づいた「民族服」を超えたところにある人類共通の「世界服」のデザイナーになるという夢への一歩を踏み出した。そればかりか、服造りという領域から解き放たれ、より幅広いデザインの大海原に船出できることになったのだ。
今日、廣川は、人間の衣服だけでなく家具や車椅子、自動車、ロボット、建造物の皮膚をデザインし、さらには人々を結びつける文化的な絆まで生み出すクリエイターとして活躍している。知らない人が見たら、一見関連のない活動をしているように見えるかも知れない。しかし、役割の定義のおかげで、廣川自身の中ではこれらすべての活動が「皮膚のデザイン」という同じ視線の延長線上に並んでいる。この統一された視点が、彼女の多岐にわたる創作活動に一貫性をもたらしているのだ。
境界を超えて:服飾デザイナーから皮膚のデザイナーへの進化
廣川の中には、服飾以外の分野に取り組もうという考えは、独立して自分の事務所を構えた時からあったようだ。かつて行ったインタビューで彼女はこう語っている。
「私が知る20 世紀の服飾デザイナー像は春夏や秋冬の各シーズンにおいて独自のスタイルを提案する衣服をデザインして、それを発表するために東京やパリ等でランウェイショーを行ない、販売してブランドを運営するイメージでした。私は、これからの二十一世紀のファッションデザイナー像はどうあるべきかを自らに問い、そこで思い至ったのは、服飾をデザインする工程で扱う発想や技能は、今後、おそらく服以外のものにも展開、応用できるだろうということでした。」
そこで廣川は服飾以外の仕事にもチャレンジしたいという想いで、まずは幅広くデザインを手掛ける会社を作り、服飾ブランドは一つの事業とすることにした。こうして作られた会社が「SOMA DESIGN」、そして同時に作られた服飾ブランドが「SOMARTA」だった。
それにしても家具や工業製品、建物のデザインがなぜ「皮膚のデザイン」なのか、と疑問に思う人もいるだろう。その点を解説するには、まず「第二の皮膚」という視点から説明する必要がある。ある程度、ファッション業界に関わったことのある人なら「第二の皮膚」という言葉は決して廣川が初めて言い出したものではないことはご存知だろう。もっと早い用例もあるが、一番有名なのはメディア理論の先駆者、マーシャル・マクルーハンが1964年に著書『メディア論―人間の拡張の諸相』の中で、衣服が皮膚の拡張であるとし、温度を調節する役割を果たすだけでなく、個人の社会的な自己を定義する手段でもあると述べており、そのことは廣川自身も知っていて、インスピレーションの一つとしている。
以前に行ったインタビューでは、学生時代に観た展覧会で「皮膚と被服」というコーナーに「第二の皮膚」の解説があり強い影響を受けた、というエピソードを聞いている。1999年、東京都現代美術館で開催された「身体の夢 ファッション OR 見えないコルセット」展にその展示があったそうで、カットソーにタトゥの柄をプリントしたイッセイ ミヤケやジャン・ポール・ゴルチエの作品等が展示されており、それが強く印象に残ったのだという。「皆プロのデザイナーになったら皮膚をデザインしている。私もデザイナーになったら皮膚をデザインしなければ」と考えていたと廣川は語っていた。
昔からある「第二の皮膚」という言葉だが、この視座を廣川以上に突き詰め、これだけ多くの作品をつくったクリエイターは他にいないはずだ。それ以上に重要なのが、この言葉の「第二」という部分に着目して、概念を拡張したことだろう。展覧会でも紹介しているが、廣川の定義によれば「第一の皮膚」は人間の生来の皮膚、「第二の皮膚」はその上に纏う衣服など個々が身につけるもの。ここまでは他でも言われてきたことだ。しかし、廣川はその先にも想像を巡らせ、「第三の皮膚」として椅子などの家具や車、飛行機といった乗り物、「第四の皮膚」を建築物などの空間、さらに「第五の皮膚」を目には見えない環境や風土、そして「第六の皮膚」をインターネットなどの仮想空間や宇宙空間とすることで幅広いデザインプロジェクトに一貫した姿勢で取り組むことができる独自のポジションを築いた。
廣川がより突き詰め、拡張した「皮膚のデザイン」の概念を誕生させたことで、「第二の皮膚」という歴史ある視点は今やその一部として包摂されてしまった。
蜜柑ネットからMoMAまで:『スキン シリーズ』誕生の軌跡と革新性
さて、そんな廣川の多種多様な皮膚のデザインの中でも最初に手掛けた作品であり、代表作とも言えるのが「スキン シリーズ」だ。まさに「第二の皮膚」の概念をそのまま形にしたような衣服になっている。
人間の皮膚がそうであるように一切の継ぎ目がない無縫製のニットは、編目構造による優れた伸縮性でどのような形の身体もすっぽりと包み込む。また皮膚の動きに合わせて伸び縮みするため、身体のどのような動きに対してもストレスが少ない。そうした着心地の良さに加えて、シワを気にする必要がなく軽量で携帯性に優れているといった特徴もあり、プロダクトとしても人気が高い。そして何よりも着る人が自らの表現として纏いたくなる美しさを備えている。廣川の手によって複雑な文様が編みの濃淡で表現されており、着る人の身体の立体感が美しく描き出されているのだ。
「スキン シリーズ」のこうした特性は一般ユーザーを魅了するだけに留まらず、舞台上で自らの身体を表現の道具として活躍する人々、特にダンサーからも高く評価されている。有名なところではマドンナ、さらにレディー・ガガが自らの舞台やミュージックビデオで身につけている。またダンスカンパニー、Noismを率いる演出振付家・舞踊家の金森穣、俳優/ダンサーとして活躍する森山未來などが何度も「スキン シリーズ」を採用した舞台を披露している。またネザーランド・ダンス・シアターで活躍後、独立し現在は個人で活動しているダンサー/振付家の湯浅永麻は「スキン シリーズがなければ、この舞台はできなかった」と語るほど「スキン シリーズ」に大きなインスピレーションを得た作品をいくつか手掛けている。
海外での評価も高い。ニューヨーク近代美術館(MoMA)は、2017 年に開かれた同館で約70 年ぶりに開催されたファッションの展覧会『Items: Is Fashion Modern?』で、肌着の新しい原型として「スキン シリーズ」を展示。それをきっかけに同館の永久収蔵品にも加えられた。廣川の一つ一つの作品の裏には膨大なリサーチと試行錯誤がある。展覧会「皮膚のデザイン」では、そうした作品誕生背景の試行錯誤も「STUDY(習作)」として展示されていることだ。
「STUDY 01」というコーナーでは、「スキン シリーズ」誕生の直接のきっかけは無縫製技術との出会いだが、実はそのはるか前、廣川は学生時代に「スキン シリーズ」のニットの構造に似た蜜柑ネットに魅了され、バービー人形に着せて実験していたエピソードなどが紹介されているのが興味深い。
デジタルと職人技の融合
「皮膚のデザイン」展は「スキン シリーズ」が展示の中心となっており、会場の外からも見える入り口正面では、これを纏った11 体のマネキンが来場者を出迎えてくれる。見渡すとひとくちに「スキン シリーズ」といっても多様なバリエーションがあることに驚かされるはずだ。
ここが廣川の凄いところで、物事をその本質まで徹底して掘り下げる力に加え、浮かび上がった本質から想像力を膨らませ、様々なバリエーションの花を咲かせる力があるのだ。「スキン シリーズ」では編目の濃淡で表現された複雑な文様の美しさが重要であることは既に述べたが、実はこれこそが「第二の皮膚」の特性だ。
古来、人類は自らを本来の自分以上の存在、自らの夢へと近づくためにボディペイントやタトゥ、刺青などさまざまな方法で自らの皮膚に装飾をしてきた。「スキン シリーズ」は、この「身体の夢」を、取り替え可能な道具である「第二の皮膚」、つまり衣服に投影することで何度でも、どんな夢でも叶えられるようにした。
まずは廣川が考えたストーリーに合わせて文様をデザインし、それをコンピューター上で身体部位を意識したデジタル設計図に落とし込む。そして、職人がニット用のコンピュータープログラムを組み、そのプログラムに基づいて機械がニットを編み立てる。こう書くと簡単そうだが、その一方で服としての構造と編みのパターン(テキスタイル)、意匠( デザイン)、型紙(パターン)といったものを多角的に見ながら同時にデザインしていく必要があり、職人(アルチザン)の刺繍などが加えられるものでは、あらかじめ刺繍による横方向の収縮率も計算して幅広い編み地で製作するといった工夫も必要になる。いずれにせよ、一般的な西洋服とはまったく異なるアプローチで作られている。
宇宙から生物まで:廣川玉枝『スキン シリーズ』が織りなす想像の皮膚
先に述べた通り「スキンシリーズ」で生み出される繊細な編み文様の表現の上に、さらに職人(アルチザン)の手仕事の技が加えられることがある。
今回の展示で編みだけで表現した「第二の皮膚」と言えば、ダイヤモンドのように賢固で幾何学的な文様の皮膚のデザイン「Adamas」(2013)と翼を広げた隼(ハヤブサ)を抽象化して描いた文様「Horus」(2014)が挙げられる。また壁際に展示されていた普段は見ることのない筋肉の流れを可視化した「Atlas」( 2018)もそうだ。
これに対して舞台正面で照明を反射しながらきらめく「Protean」(2007)や「Clematis-Metal」(2007)は職人がスワロフスキークリスタルやメタルチップを一つ一つ貼り付け、ミクロがマクロの宇宙になる着想からデザインされた「Microcosmographia」(2010)や羽をイメージした文様の「Crow-Bijou」( 2011)ではビーズやスパングルを手刺繍、インドの伝統的なヘナタトゥ・メヘンディを表現した「Frost-Mehendi」(2008)ではハンドペイントと銀箔を施し、架空の民族をテーマに、トライバルタトゥの文様を図案化した「Tribal-SOMA」(2016)などその他のモデルでも職人が箔押しをするといった具合に、機械仕事と手仕事を融合させて唯一無二の皮膚を表現している作品も多い。
これら一つ一つの文様の美しさにも目を惹かれるが、ミクロとマクロがつながった宇宙や架空の民族のタトゥなどそれぞれのテーマ設定も面白い。
特に興味深いのは、鱗や甲羅のように硬質でプロテクターとなる鉄のような肌を表現した「Clematis-Metal」や羽をイメージした「Crow-Bijou」、昆虫や爬虫類の肌に着想を得た「Reptilia」(2017)など他の生物にインスピレーションを受けたシリーズで、これは廣川が自然界の動植物の皮膚の美しさに魅了され、常に着目してきたことを感じさせる。
作品誕生背景に迫る「STUDY 02」のコーナーでは、ルーペ越しに見る玉虫色の昆虫の外皮や繊細なビーズ刺繍で甲殻類の皮膚を表現した試作模型を見ることができる。
皮膚を超えて
廣川が抱く人間の肉体の興味の対象「皮膚」だけに留まらない。
「STUDY 03」では、「Atlas」で表現を試みた筋肉の機能美への関心について、そして「STUDY 04」では、人間の身体構造を決定している骨格への興味、特に人間がなりたい姿に成るべく自らの身体の改造を試みてきた歴史に触れ、同じ「スキン シリーズ」でも、異なる動物の骨格に被せると、また別のもののように見えることを示している。
2008年、廣川は「進化した身体」をテーマに、人間の体をさらに美しく見せる新しい「骨格」をデザインする。実際の体の上に身に着けることができる骨格、「Evolution-Body : Transformer」で、この骨格の上から「スキン シリーズ」のドレスを着ると、伸縮性のあるニット素材が骨格にぴったりとフィットし着る人に新たな身体のフォルムを与える。
この「外骨格」も廣川の作品に度々登場する重要な概念だ。実は同じく2008年、廣川はもう1つ骨格の作品を作っている。「Skin+Bone Chair」と名付けられた花びらのような形の椅子の骨格だ。この骨格の上にこの椅子用に作られた「スキン シリーズ」を纏わせると、骨格と皮膚の間に生まれる空間が柔らかなバネの働きをする椅子のフォルムが現れる。「スキン シリーズ」の皮膚を脱がせて骨格構造は単体でスチールの椅子として楽しむこともできれば、新たな皮膚を纏うことで色や文様などの変化を楽しむこともできるという秀逸なデザインであり、廣川による「第三の皮膚」として最初期のもので、代表格の作品でもある。この年、ミラノデザインウィークのCanon「NEOREAL」展に出品された。
それ以前の作品も見ていたが、私はこの展覧会で初めて「SOMARTA」や廣川玉枝の名前を認識した。そのため、この展覧会の直後から廣川が衣服以外のデザインも手掛けるデザイナーとして注目され、自動車やロボットなど様々なデザインのプロジェクトで活躍を始めるのを目の当たりにすることになった。
椅子と並んで展示されていたZoff とのコラボレーション「Skin+Bone Glass」も、そうしたプロジェクトの1つで「骨格」と「皮膚」の視点でデザインしたアイウェアとなっている。
拡張を続ける「皮膚のデザイン」
「皮膚のデザイン」展は2つの部屋で構成されている。最初の部屋が主に「スキン シリーズ」の展示で、上で触れたもの以外に制作のプロセスを見せた展示もある。
もう一つの部屋が今回の展覧会のために作られた大型の新作、「SOMA-HOUSE」( 2024)を中心とした展示だ。
今回の展覧会を開催するに当たって廣川には一つやりたいことがあった。来場者に実際に「スキン シリーズ」を纏ってもらい、その文様の変化や伸縮性、触り心地などを知ってもらうということだ。といっても、本物の「スキン シリーズ」の服を脱ぎ着してもらうわけにはいかない。
そこで会場では「スキン シリーズ」を実際に手で触って触感を試せる体験ゾーンも用意された。さらに実際に纏ってもらうべく作られたのが、中に入ってくつろぐことができる巨大な「SOMA-HOUSE」だ。
このように「スキン シリーズ」を建造物に使った例はこれまでにもあり、2023 年には高野山で開催された芸術祭「高野山アートデイズ 2023」で曼荼羅を立体的に展開した仏塔、「Mandala Tower」を製作した(STUDY 05 )。大きな構造体だったが、中央には塔があり高い台座の上に置かれているために制作者以外は中に入ることができなかった。
この「スキン シリーズ」の構造体の中に、来場者に入ってもらう方法はないか。試行錯誤を重ねて新たに作られたのが軽くて頑丈、そして運搬もしやすく組み立てやすい段ボール素材の外骨格だった(STUDY 06)。この展示を置いたことで展覧会は廣川が手がける「第二の皮膚」から「第四の皮膚」までの皮膚のデザインを総覧できる初の展覧会として故郷の藤沢市に錦を飾ることとなった。
なお、廣川は2021年には「第五の皮膚」と呼べる作品までつくっている。大分県別府市で開催された個展形式の芸術祭「廣川玉枝 in BEPPU」では、コロナ禍で大打撃を受けた観光地で疫病退散を祈り、地域の人々を一つにつなぐ祭(=神事)を創出した。日本古来の伝統的な祭の成り立ちを研究して、その儀式や祭に登場する来訪神・まれびと達の衣装、さらには会期中、鉄輪温泉の主要な建物に装飾を施し、その印象を一変させる「第四の皮膚」まで全てをデザインし、そこで実際に祭の儀式を執り行ったことで、これがその地域の人々を一つに繋ぐ「第五の皮膚」となったのだ。
廣川が創出した四つの神事の内の一つ「地嶽祭」が始まり、まれびと達が太鼓を鳴らしながら街を練り歩き始めると次々と人々が家から出てきて最終到着地点にはコロナ禍とは思えない物凄い人だかりができていた。そして、まれびと達と地元の子ども達との間で自然な掛け合いが発生し、終演時には参加した観客から喝采が自然と湧き起こり、その場を共有していた人々が一つの輪で繋がっているのを強く感じさせた。今回の展覧会ではこの展示が省略されたが、鉄輪温泉では今でも祭を復活させて欲しいという声が上がり続けている。
この「in BEPPU」は、映像作品としてウェブ上にアーカイヴ化されており、廣川が創り出した祭を今でも見ることができるので、実際に祭の興奮を感じてみて欲しい。(廣川玉枝 in BEPPU https:// inbeppu.com/2021/)
廣川は仮想空間や宇宙空間を覆う「第六の皮膚」についても語っている。いずれ、それを手掛ける時が来たら、廣川はいよいよ誰にも無視できないデザイナーになっているのかも知れない。
だが、それを待たずとも既に世界中の人々の目に触れた廣川の作品があり、今回の展覧会でも二つの部屋をつなぐ通路に展示された。東京2020オリンピック・パラリンピックで表彰台に立つ日本人選手が着用した公式のポディウムジャケットだ。廣川がアシックスに協力し、身体を美しく見せながらも熱や紫外線から保護し、呼吸ができる皮膚のような編み地のデザインを考案して製作した。
長年「スキン シリーズ」で培われてきた技術が、国や大企業からも認めたことがわかる事例であり、こうした極めて機能的なジャケットにも応用できることを示している。
ますます大きな注目を集め活躍の幅を広げている廣川は、現在も多くの人が目にするであろう数年がかりのプロジェクトに関わっており、今後もニュースなどでその活躍を目にすることが増えるはずだ。その時、彼女の製作の裏にある「皮膚のデザイン」に思いを馳せてもらえればと思う。
20 世紀まで、人類にとって「皮膚」はしばしば境界線として機能し、人々を分断し、不必要な争いを引き起こしてきた。廣川玉枝が考えるコミュニティや宇宙をも包み込む「皮膚」という視点が広まれば、より調和の取れた平和な世界が実現するかもしれない。
あとがき
この記事の英語版を公開直前に、2025年大阪万博の石黒浩シグネチャーパビリオン「いのちの未来」に廣川さんが関わることが正式に発表された。実は石黒パビリオンのチームは、廣川玉枝展の期間中、藤沢市アートスペースも訪問している。この時、廣川さんが大分で始まる展示の準備で現地に来れないということで、代理で私が展示の説明をすることになったが、皆、展覧会で廣川さんとどのようにさらに協力を深められそうか良いヒントを得ていたようで、万博開催が今から楽しみだ。
一方で、記事英語版の公開直後に悲しい知らせも舞い込んできた。
ファッションジャーナリストの川島蓉子さんの訃報だ。
私が廣川さんとつながるきっかけとなったのは、12年前に川島さんが設立した「ifs未来研究所」だった。
今日、多くの未来は企業の利潤追求の論理の上で作られています。
それを使う人たちの気持ちと乖離したところにパッと湧いて出る未来。
これに対してifs未来研究所が目指していたのは、今日の日々の生活と地続きの未来。
川島蓉子さんが自ら一人一人ハンドピックした7人の外部メンバーを初期スタッフとして設立された。
最近では帝国ホテルリニューアルを手掛けることでも注目を集めている世界的建築家の田根剛、SOMA DESIGNの廣川玉枝と福井武、プロダクトデザイナーの酒井俊彦、当時まだ20代だった天才肌のtakram design engineeringの渡辺康太郎、コーネル大学SGEセンター研究員の唐川靖弘、そしてテクノロジーに懐疑的なテクノロジージャーナリストの私、林信行というかなり色とりどりの7人だった。
三越伊勢丹、LUMINE、BEAMS、そして日本の老舗羊羹ブランド「虎屋」など、幅広い企業とともに心躍るプロジェクトに取り組んだ。
この研究所での活動は、テクノロジー関連の仕事の連鎖からなかなか抜け出せずにいた私に、もっと広い世界へと踏み出す大事な一歩となってくれた。
(中でも代表的な仕事はこちらだ:みらいの夏ギフトでテクノロジーのワクワクをもう1度
この記事を、廣川さんとの縁を頂いた川島蓉子所長に捧げたいと思います。
川島蓉子さま、改めて感謝すると同時にご冥福を心よりお祈り申し上げます。