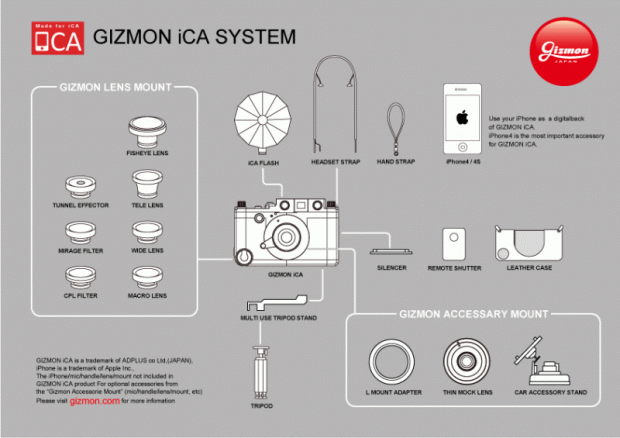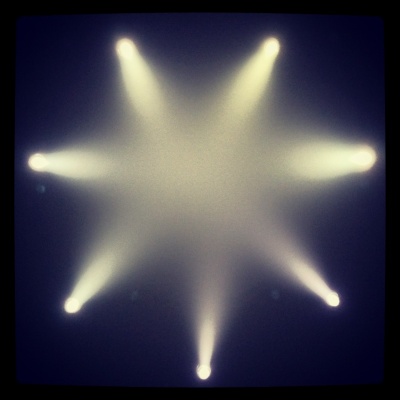基準は自分でつくる!〜UPの取材で思ったこと
日々の運動量と食事、睡眠を記録するJAWBONEの「UP」がついに国内でも発売された(予約が始まっただけで、実際の発売開始は4月20日から)。
眠りの浅い深いを記録し、もっとも心地よく起きれるタイミングで、音を鳴らさずバイブレーション機能で起こしてくれる、というこの機能だけでもかなり人気の製品だ(個人的には、午後も快活に過ごせるようにパワーナップ(仮眠)を支援する機能も素晴らしいと思う)。
製品の国内発売に先立って、担当者が来日し、インタビューに応じてくれた。
詳しいインタビューの内容はケータイWATCHをはじめ、他所でも紹介されているので、そちらを参照してもらうとして、私は製品説明の場での「防水」についての話が心に残ったので、記事にしたい。
ここ数年、「防水」と言えば「日本のケータイメーカーの強み」というのが、国内家電メーカーのジョーシキだ。
日本で7〜8年前に松村太郎氏らが行った調査でも、女子大生(今は社会人?)がシャワーを浴びながらもケータイを使う、といった調査結果もあり、お風呂やシャワーの最中でも使える防水機能が重要とされてきた。
一度、どちらの方向に進めばいいかを示されると、その方向に対して、黙々と技術を洗練させるのが日本企業のいいところ。日本は非常に高い国際基準のIPX5やIPX7といった基準をクリアするケータイがもはやジョーシキになり、国際ケータイのほとんどのモデルが防水対応になった。
バルセロナで毎年開催されるケータイのイベントでも、日本メーカーのブースに行くと、海外製品にはない、その強さをアピールすべく、ケータイを水槽の中に展示していたり、水をかけたりしている。
確かにその技術は凄いには凄いが、そのおかげで日本製のケータイは、すべて電源端子の部分に面倒なプラスチックキャップがついており、充電の度にそれを取り外さなければならない。
ほとんどの人にとって、年に何回やらかすか わからない水没に備えて、毎日行う充電作業が非常に面倒なことになっている、という事態が続いている。
しかも、この高度な防水は、この少し大変なキャップを完全にハメる、という状態が守られて初めて保証されるもの。充電する際に面倒だからと、充電端子カバーを緩めに押し込んでいた状態では、表示されている防水性は守られていないのだ。
私は数年前から、そんな「スペックシート」で優位を示すためだけの防水性に疑問を感じ始めた。
そんな頃、海外のイベントでは、ナノコーティングという技術を使って、ケータイ電話の基板そのものを、コーティングしてしまうという技術が話題になり始める。
この技術を使って加工すれば一見、素の状態に見えるiPhoneが、そのまま水の中で使えるようになってしまう。