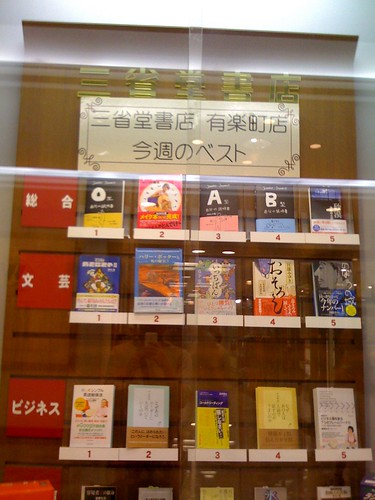ゆるいコミュニケーションが楽しい
AMNでおもしろいバナー広告が始まった。
nobilog2のトップに表示されるAMNのバナー広告(表示されない場合は、こちらをクリック)に、これからしばらく「〜〜があればもっと自由になれる」というバナーが表示される。
(毎回ではなく何回かに1回の確率)
まず最初は、私がアンケートに答えて書いた内容が表示され、
その後、読者の方がお題に対しての自分の答えが書き込める状態になる。
ここで、あなたバージョンの「〜〜があればもっと自由になれる」を書き込むと、
その後、書き込んだ内容がバナーに表示される。
さらに、その後には、他の人が書き込んだ内容が表示される。
試しに私も人気ブログ「ネタフル」のトップに自分の名前を表示してみた(笑)

(「ショップ」の「ップ」が切れてしまった)
お題を通してブログの他の読者とのゆるいコミュニケーションが楽しめるこのバナー広告、
なかなかおもしろいアイディアじゃないかと思った。
(私はマジメくさった答えを書いてしまったが、もうちょっとウィットを利かせればよかったと後悔)。
ちなみに、こちらのページから、他の人の投稿を一覧形式でみることができ、投票も可能だ:
あなたにもっと自由を
これ、むか〜し、昔、家庭用ビデオカメラが発売され始めた頃、
電気屋さんでカメラに写り込む自分をみたかのような感覚に近いのかもしれない。
そういえば、昨年のFoo Campで友達になったダン・アルブリットン(綴りがわからない)の携帯電話参戦型マルチプレーヤーゲームの夢にもなんか似ている。
彼は渋谷の交差点にある巨大スクリーンに、交差点にいる人が、その場で電話をかけて参戦できるマルチプレーヤーゲームをやってみたいという夢を語っていた。
彼はAsteriskという技術とMegaPhone 3000というプラットフォームで、こうしたゲームをつくっていた(詳しくはこちらのFoo Campのレポートを!って、それほど詳しく書いていないけど:
Foo Camp―GoogleやWikipedia創業者も参加するオライリー主催プライベートイベントの全貌【後編】)
(ちなみに私は今年のFoo Campには参加していないが、伊藤穣一さんが参加してきたようだ。うらやましい
JOI ITO:FOO Camp 2008に行ってきた)
nobilog2のトップに表示されるAMNのバナー広告(表示されない場合は、こちらをクリック)に、これからしばらく「〜〜があればもっと自由になれる」というバナーが表示される。
(毎回ではなく何回かに1回の確率)
まず最初は、私がアンケートに答えて書いた内容が表示され、
その後、読者の方がお題に対しての自分の答えが書き込める状態になる。
ここで、あなたバージョンの「〜〜があればもっと自由になれる」を書き込むと、
その後、書き込んだ内容がバナーに表示される。
さらに、その後には、他の人が書き込んだ内容が表示される。
試しに私も人気ブログ「ネタフル」のトップに自分の名前を表示してみた(笑)

(「ショップ」の「ップ」が切れてしまった)
お題を通してブログの他の読者とのゆるいコミュニケーションが楽しめるこのバナー広告、
なかなかおもしろいアイディアじゃないかと思った。
(私はマジメくさった答えを書いてしまったが、もうちょっとウィットを利かせればよかったと後悔)。
ちなみに、こちらのページから、他の人の投稿を一覧形式でみることができ、投票も可能だ:
あなたにもっと自由を
これ、むか〜し、昔、家庭用ビデオカメラが発売され始めた頃、
電気屋さんでカメラに写り込む自分をみたかのような感覚に近いのかもしれない。
そういえば、昨年のFoo Campで友達になったダン・アルブリットン(綴りがわからない)の携帯電話参戦型マルチプレーヤーゲームの夢にもなんか似ている。
彼は渋谷の交差点にある巨大スクリーンに、交差点にいる人が、その場で電話をかけて参戦できるマルチプレーヤーゲームをやってみたいという夢を語っていた。
彼はAsteriskという技術とMegaPhone 3000というプラットフォームで、こうしたゲームをつくっていた(詳しくはこちらのFoo Campのレポートを!って、それほど詳しく書いていないけど:
Foo Camp―GoogleやWikipedia創業者も参加するオライリー主催プライベートイベントの全貌【後編】)
(ちなみに私は今年のFoo Campには参加していないが、伊藤穣一さんが参加してきたようだ。うらやましい
JOI ITO:FOO Camp 2008に行ってきた)